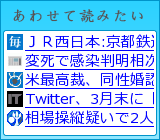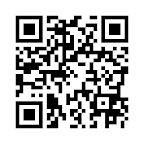東京Jazzに行って学んだこと
東京Jazzという3日間のイベントに行ってきました(日曜の夜だけ)
http://www.tokyo-jazz.com/
情操教育の一環として子どもも連れて行ったのですが,19時開演で4バンドが出演予定.1つめが終わったところで50分+15分休憩...全部終わったら何時?
結局最後のバンドの途中で退出,勿論館山まで戻ったら深夜1時前.
子ども達よ済まん!明日(今日)学校・幼稚園なのに!
どうかjazzのこと嫌いにならないで.
Jazz playerとして,家庭医として色々と思うところがありましたので少し.
Jazzについて
1.現在のjazzは複雑になりすぎている.
芸術の一つである以上originalityを追求することが必要で,特にJazzはこれまでの流れに自分らしさを乗っけて新しい「何か」を生み出すことを要求されるので,ともすれば,「良い物を作るための破壊」ではなく「破壊のための破壊」になってしまっていることがある.
間違いなく自分ではマネなどできっこないレベルだがそれだけ.面白くない.
かなり自慰的なartistもいたように思います.すごいことは分かるが,理解できなくなったら一部の人だけの物になってしまう.
一方で3つめのLou Donaldsonのバンドはすごかった.昔のまま(60年代)の昔のヒットソングで,昔の通りやるんだけれど,観客の反応が最も良かった.観客が一番正直.the less is the more. the simple is the best.
jazzは小さなライブハウスで息づかいの分かるところで聞くのがベストなので,今回のような何千人も入るところではやっぱりダメだな,artistがあんなに遠いもん.そのせいで自分は面白くないんだ,と思っていたら,Lou Donaldsonは観客がみんな入り込んで,感情移入して.ホール全体が一体化.
Duke Ellingtonの言葉が思い出される.「世の中には2種類の音楽しかない.良い音楽と悪い音楽だけだ」
大衆に受けなくなればその芸術はそのまま廃れてしまう.
2.エンターテイメント(娯楽)と芸術
そんなことを考えながらコンサートを聴いていたら,死後まで価値の認められなかった画家ゴッホのことやら,理解されにくいピカソやダリのことを思い浮かべていた.
パリはもちろんのこと,東京の露店でも写実的なもしくは印象派ぽい油絵はそれなりに手軽に手に入る(勿論無名のartistだけれど).基本的な技術が有れば恐らく描ける類の絵.それは芸術と呼べるのか.そこに費やした制作時間(基本的な作業時間とキャンバス,絵の具代)以上の価値はあるのか.一方で現代美術館にあるようなコンテンポラリーアート(恐らくフリージャズや,現代の多くのjazz musicianはこれに相当する)は一見理解できない物も多く,お金を出す気も起きないか,ひょんな事でお偉い批評家に取り上げられて,とてつもない値が付くかのどちらか.
芸術家であること(originalityを追求すること)とエンターテイナーであること(大衆に広く受け入れられること)は両立するのか.
1つめのバンドは芸術的なレベル,技術レベルはとてつもなく高かったが,聴衆と分かり合えたか,聴衆に伝わったかは疑問.いわゆる自分の価値観の押しつけのような.(一方的なパターナリズムの医療の風景を見ているよう)
Lou Donaldsonは往年のテクニックにこそかげりは見えていたが最も聴衆とつながっていた.最も聴衆が喜んだ,満足した.
commodity化の話は以前も書いたので
芸人と芸術家の違い(goods, service, experience)
これ以上は書かないが.
大衆性(大衆に受けること,幅広く行き渡ること)と希少価値(one and onlyであること)の両立は限りになく不可能に近いのではないかと考えている.
医療をやる上で,自分が家庭医としての技能を磨く上でこれが永遠のテーマのように思える.
家庭医療とのからみ
1.海外の大御所を呼べばそれで何とかなると思っている
確かに今回のチケットも最も大御所の名前の多い回を選んだのは自分なのだが(そのせいで子ども達に迷惑が),某大御所ピアニストはミストーンだらけ,某ギタリストとのコラボは明らかに打ち合わせ不足,しかも2人とも「こなし」「流し」の演奏.
忘れてしまっていた「年取ったかつての大御所の演奏は失望のことが多い」の原則を再認識することになった(勿論例外もあるのだが)
残念ながら,何千人というホールを埋めるには出来るだけ知名度の高い人を目玉に据える必要があるのだが,そういう人が最もコストパフォーマンスが悪い.限界効用逓減の法則ということもあり,有る程度の金額を超えると追加して投入する資源に対してのリターンはだんだん減ってくるが,出した金額に対しての見返りの期待は通常限界効用逓減が起きないので,期待と現実のギャップが大きくなる.図でかけるとよいのだが..
ともあれ,家庭医療に限らず,医学に限らず,海外の物・人が珍重されてしまうが,それはある意味人寄せパンダでしかなくて,ずっと効率よく近場から,質の高い講演や指導医を確保することは出来るはずなのに.
単発の講演やセミナーが気合いやエネルギーを注入する以上でも以下でもないことはもうみんな知っているはずなのに.
食べ物だけではなく,人という資源においても自給率(指導医国内自給率,指導医施設内自給率)といったことやフードマイレージに相当するヒューマンマイレージ(その講師,指導医を読んでくるのにかかるコスト)を考慮した,人的資源の地産地消(千葉県では千産千消といいます)を考えていかなければならないのではないか.
2.家庭医療とjazzの類似性
Clinical Jazzという教育法が家庭医療の世界にあります.臨床という医療行為とjazzとの相似性を良く表していますが,jazz playerとしては,jazzを知らない人がアドリブだコードだという表現を使うのを聞くことには何となく違和感があります.(非常に表面的に感じます)
私はjazzと家庭医療はもっと深いレベルで共通点を持っていると考えています.
jazz legendの一人チャーリーパーカーの言葉
Music is your own experience, your thoughts, your wisdom. If you don't live it, it won't come out of your horn. ~Charlie Parker
音楽はおまえ自身の経験であり,思考であり,知恵なのだ,音楽を生きるという行為なしに,それはおまえの楽器からは出てきやしない.
→人生経験が豊富でなければ,自分の人生と真っ正面に向き合わなければ,その人の医療行為も薄っぺらい物になる.
そして現代のlegend winton marsalisの言葉
jazzをうまくやるにはまず音を出すのではなく,周り・相手のいっていることを良く聴くことだ.それなしにjazzは始まらない.
→補足不要ですね.まず患者さんの話を良く聴きましょう
長くなりましたが,非常にコストパフォーマンスの悪かったコンサートで腹が立ったのでとっても批判的なエントリーになってしまいました.
それでも,大衆に受けなくなればその芸術はそのまま廃れてしまう.
さて振り返って,
家庭医療はきちんと大衆に受けること(患者満足度)とその芸術性(学問としての家庭医療と質の高い医療)の両立を目指しているか.
P.S. 成人はあらゆるところで学ぶのであった.