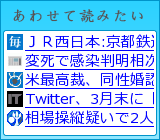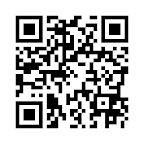尊敬する先輩のblogに触発されて昔読んだコンセプトを思い出した.(positive showerがあふれ出る先輩で会うといつも元気になるので大好きです)
後半の麻疹対策もそれはそれで,目を見張るのだが,質改善のための方法論について
問題ばかりが目に付くとnegativeな報告や会話になりがちですが、「うまくいっている病院をモデルにしてみよう」というやり方もありますね。
成果=Evidenceは説得力があります。
「ICUの抗菌薬使用量が半減」「広域抗菌薬は年一桁」というような病院が実際にあるわけです。
Best practice modelにはいろいろあります。「言語化」できるかどうかはひとつのカギです。できる人たちだけやればいいわけではありませんので。
残念ながら引用が出来ないがおそらくいつぞやのHarvard Business Reviewだったと思う
postitive deviance/deviant
についての記載があった.そこで挙げられていた例はある保険会社が全体にどの営業所も軒並み売り上げが落ちている中で,なぜか一つだけ売り上げを伸ばしている営業所があった.そこのやり方が他の営業所と何が違うかを徹底的に調べて他の営業所ではやっていなかった行動を他の営業所に取り込む,という事例で,その一つだけ飛び抜けている営業所のことをpostitive deviantと呼ぶ.
同じような症例が下記の本で紹介されていたと思う.(定かではないが)
ファーストフードのチェーン店で同じような来客数なのに売り上げに大幅な差がある2店舗に実際にいって,何が違うかを観察すると,売り上げの多い方は「もう一品いかがですか」「サイズは大きくしますか」などのお勧めのせりふが毎回確実に言われていたが,低い店はそれが徹底されていなかったとのこと.(やっぱり意味あるんですね)
本当にそれが売り上げの差の原因なのか,他の要素に差はなかったのか,交絡因子は?という反応をするのがほとんどの医師.
質改善の活動と研究は別物である
ということが理解されていない.というより,「質改善活動」そのものを体系立ててはこれまでの医師は教わったことがない.質改善活動は良くなりそうで,出来そうなことはとりあえずやってみる,それで良くなれば続ける,相でなければ方法を再検討する.というやり方で,結果として現場が良くなれば良し,とする立場.
その事の詳細はまたの機会にするとして,
postitive deviance/deviant
という言葉は未だ日本語にはなっていないし,それほど浸透してもいないようである.
ただ,「best practice modelから学ぶ」という言葉はある.基本的には同じ.
Positive Deviance Initiative
より,
What is Positive Deviance?
In every community there are certain individuals (the "Positive Deviants") whose special practices/ strategies/ behaviors enable them to find better solutions to prevalent community problems than their neighbors who have access to the same resources. Positive deviance is a culturally appropriate development approach that is tailored to the specific community in which it is used.
「find better solutions to prevalent community problems than their neighbors who have access to the same resources.」というところがみそ.やはりあまりにも違いすぎる状況では何がその差を生んでいるのかわからないので.
positive deviant network
から
The first successful large-scale field application of positive deviance was initiated in Vietnam in early 1991 to address the problem of childhood malnutrition. Over the following decade, the positive deviance approach to nutrition became a national model and today reaches a population of 2.2 million inhabitants in 250 Vietnamese communities.
Positive Deviance
From Wikipedia, the free encyclopedia
より
Positive Deviance (PD) is an approach to personal, organizational and cultural change based on the idea that every community or group of people performing a similar function has certain individuals (the "Positive Deviants") whose special attitudes, practices/ strategies/ behaviors enable them to function more effectively than others with the exact same resources and conditions.[1] Because Positive Deviants derive their extraordinary capabilities from the identical environmental conditions as those around them, but are not constrained by conventional wisdoms, Positive Deviants standards for attitudes, thinking and behavior are readily accepted as the foundation for profound organizational and cultural change.
いわゆるヒーローと言うことかもしれません.ただし,positive deviantが必ず目立っているとは限りません.
For example, even though poverty is often the root-cause of ill health, in any community there will usually be some families, the Positive Deviants, that manage to stay healthy, or raise healthy kids, despite their poverty. Their practices, such as washing their hands more often, cooking the food differently, consuming crops that were considered taboo by the rest of the village etc. became the foundation for large scale community change.
あそこは患者さんの病状が軽い人が多いから.指導医がいいから.医者のできが違うから.スタッフが潤沢だから.うちの方が難しい患者の症例をかかえているから,等の言い訳をするのは簡単だろう.
しかし,いいわけをしたらその時点で改善の種(チャンス)は消えてしまう.
「~だからxxできない」では,そこで頭脳の活動がストップするが,そうではなく「どうすればxxできるようになるか?」からはじめるだけで,頭がフル回転をし始める.同じ状態をどのようにとらえるかが成功者とそうでない人との違いである,とは,すでに古典となったロバートキヨサキの著書より(後述)
再度wikipediaより
Their extensions include methodologies and technologies for:
*Quickly identifying the Positive Deviants
*Efficiently gathering and organizing the Positive Deviant knowledge
*Motivating a willingness in others to adopt the Positive Deviant approaches
*Sustaining the change by others by integrating it into their pre-existing emotional and cognitive functions
*Scaling the positive deviant knowledge to large numbers of people simultaneously[
結局その道の達人を見つけ,ノウハウを言語化し,その他の人がそれをまねしようという気持ちにさせ,それを思考過程レベルで習慣化させ,大きな規模に広げる.
組織変革の話になってしまいます.
最後に医学の世界での使用例を(とうぜんあります)
MEERA SHEKAR et al. Use of Positive-Negative Deviant Analyses to Improve Programme Targeting and Services: Example from the TamilNadu Integrated Nutrition Project.International Journal of Epidemiology 1992, 21: 707–713.
The power of positive deviance -- Marsh et al. 329 (7475): 1177 -- BMJ (BMJにアクセスすると必ずブラウザがクラッシュするのでabstractすら読めてませんが)
飛び抜けたケースを「例外」といって除外するのが量的研究の指向(いいすぎかも)
「なかまはずれ」に意味があるとして,それ自体をよく見たり,なぜ生じたか考えるのが質的指向.