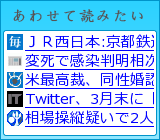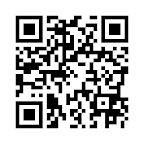日本家庭医療学会,日本プライマリ・ケア学会の学術集会抄録の締切が29日に迫っている.
うちのレジデントやHANDS-FDFの修了生達とコラボで(主にお手伝いだが)発表をする予定であるが,締切に向けて,抄録の確認をする作業が中心である.
抄録を書く際に色々と自分で気をつけていることがある(それらを中心にアドバイスをするのであるが)
形式がワークショップ,口演,ポスター(学会によっては研修プログラム紹介も)によって多少違うとは思うが,共通する部分だけ書き出してみよう
意識しなければならないこと
誰に対して抄録を書いているか
1.学会の運営に関与する人:要は応募がいっぱいだったときに採否の判断をする必要が出てくる
2.当日の学会の参加者:それを呼んで興味を持ってもらう必要がある
3.その他:偶然も含めて抄録を手にする人
この三者が抄録を読むときにどのような判断を行っているかというと
1.採否を決める人,委員会
学術集会はその学会のshowcase(展示会)であり,その学会の質や性質,雰囲気を表すものである.採否に当たり,まずは気にすること
内容の質がよいか
学会の代表として出して恥ずかしくないか
学会員のニーズに合うか(質がいくら高くても,学会の使命や,対象領域と外れていてはだせない)
など
2.当日の学会の参加者
自分のニーズと合っているか
しかも新たな学びや出会いがありそうか(知っていることしかなければ時間の無駄)
要は時間対効果があるか(同じ時間帯で重なっている他の発表や,ワークショップに対して)
3.当日の学会の参加者で,最終的にその発表は聞かない人(他のものを優先した人),当日は参加しないが抄録を読む可能性のある人
自分にとって興味があり,重要な内容か
発表者とコンタクトをとって詳しい内容を聞いたり,資料をもらえないかお願いする価値はあるか
そのときにどのように連絡を取ればよいか(ネットに所属の住所や電話番号,メールなどがある,もしくは電話番号案内で調べられるのであれば名前と所属だけでよいだろう.)
自分でそのことについて調べるときに参考となるキーワード
といった感じだろうか.
難しいのは,学会の運営者(採否の審査をする人)にはしっかり内容や質の高さをわかってもらわなけばならない(そもそも採択されなければ始まらない)ので,できるだけその判断ができるように詳しく書かなければならないが,抄録だけで全てがわかってしまうと,当日の参加者にしてみればそれで全てがわかってしまったり,ネットであとから調べればすみそうだ,ということになれば,わざわざ行く必要がない,ということになり他の発表が優先されてしまう.(実際個人的には,どの発表に行かないか,ということばかり考えているので,抄録だけで全部がわかる,概略がつかめるものには足を運ぶことはありません.知り合いが発表してそのサポートのために行くのは別.)当日来てくれた人には,より詳しい情報が手にはいるとか,抄録で「おそらくこのようなないようかな」とおぼろげに期待していた以上の収穫があるとかがないと「来てよかった」ということにならないので,どれだけ抄録に書くか,というのは意外と難しい.
STFMでは応募の際に,抄録に付け加えて,結構な枚数の詳細を提出しなければならない.抄録の字数は制限があるが,それだけではやはりどの発表を採択するか決めるには情報が不十分,ということなのだろう.このようにできていると,当然抄録と詳細の読者がちがうので,非常にやりやすい.抄録は上記2.3.の人たちを対象に,できるだけ当日きてもらえるような工夫を.詳細は(研究の場合はほぼ論文になる程度のものを,ワークショップの場合は進行計画書から,主旨,目的などまで)採択してもらえるように本気で全部書くことができる(これは一般に公開されない.ただ応募の段階でかなり詰めているので,抄録だけ出しておいて,当日が近づいてデータの分析をするとかいったあわては生じない.そもそも結果の出ていないものは学会に出すべきではないのだが.)
そこで,そもそもなぜ学会で発表するのかというところにやはり立ち返らなければならないのだが,理由はいろいろあるだろう.
1.発表者であれば大義名分を持って仕事が休める.
2.発表者であれば学会の参加費用をある程度払ってもらえる
3.多くの人に是非知ってもらいたいと思っていること(研修プログラムについて,研究でわかったことについて,日常の診療で工夫していることについて,など)を伝えたい.
4.自分が熱意を持って取り組んでいること,悩んでいることと同じようなことに興味を持っている人とネットワークを作りたい.
5.枯れ木も山のにぎわい.履歴書のエントリーとして必要(特に大学にいる人たち.つまりscholarshipの証明として)
このぐらいだと思うが,そのどれかによって違ってくるだろう.1.2.5.であれば採択されることが最終目的なので,全てを書いてしまってよいと思うが,3.4.のように当日たくさんの人に来てほしい,ということであれば,やはり抄録で全てわかってしまわない(かつ,その発表を気かなければ,と思わせる必要があるが)ことも大事であろう.
まあ,抄録の字数は通常制限があるので,意図的に削らなくても,だいたい全ては入らないので,取り扱っているトピックが十分重要度や話題性の高いものであれば,必然的に,「もっと詳しく聞く必要がある」と思わざるを得ないと思われるが.
再度まとめると
自分のニーズにあうかどうか判断できるだけの具体性(来てみて全然思っていたものとちがうと満足度が下がる)
かつ抄録だけでは今一つ理解できないので/もしくは面白そうなので是非参加してみたいと思わせる表現
当日参加者の期待を越えられるだけの内容とサプライズを抄録から外しておく
当日他の興味有るセッションとぶつかって、参加を断念した人にも伝えたいメッセージ
当日他の興味有るセッションとぶつかって、参加を断念した人、参加した人が資料を希望したり、質問がある時に後からその内容にたどりつける手がかり(所属や名前、連絡先、キーワードなど)
といったあたりに落ち着くだろう.
まあ,どうひねったところでテーマが全て,というところはあるのだけれど.
診療所や一つのプログラムで少人数を対象にやった取り組みなどどうせEBM的には価値がないので発表しても無駄だ,という考えに対して
scholarship of discoveryという意味では確かにレベルが低いだろう,しかし学術活動はそれだけではない.
(4つのscholarship参照.)
「自分が興味を持っていることについての情報を効率よく集めるにはまず発信することだ」
そのテーマに興味やこだわりがある人が反論をくれたり,「こんな取り組みをしています」「xxxxという人は知っていますか?同じようなことをしているので連絡をしてみたら」「私も興味あるので今度一緒にやりませんか」などの自分で一生懸命探していても見つからなかった情報やチャンスが飛び込んでくる.同じ興味を持つ人とのネットワーキングを効率よくするには発表するに限ります.
どのタイプの学術活動(scholarship)であっても,それはdissemination(普及)もって初めて価値を持つ,というのはとあるacademicianの言葉.全くそう思う.どれだけいいことをやっていても知っていても,それがどれだけの効果を持つかというインパクトが重要.以前にそのことは少し書いた
そのことは現在の情報の価値が静的情報ではなく動的情報に移行していることとも呼応する.
つまり情報は人と人の間を行き来してその関係性とcontextの中で初めて価値を持つ.ということ.「これすごくいいアイデアだから,もっといい形にして論文にしよう」と隠し持ってなかなか取り組めず,気がついたら,他の人が同じような内容で発表していたり,すでに時代遅れになってしまったりしたことはないですか?(私はいっぱいあります)
だから,ちょっとした種であっても,とりあえず一度人に投げてみる.そこで揉んでもらう.ネットに上げて世界中に揉んでもらう.それがalways beta versionというweb2.0的なこと.
ただそれができる前提としてく動的情報の後半に書いてある「バルネラビリティ」と「自発性」.これについては最近ずっと考えているボランティア精神と密接に結びついているのであるが,またの機会に.
数日ですが抄録がんばりましょうね,皆さん.発表することが大事です.
ちなみに静的情報はこちら
まだまだこれにこだわっている古い人たちがいます.残念ですが.
2008/02/27
抄録の書き方,情報の価値
2008/02/05
インパクトファクターと読者数(academic value vs fidelity)
書き始めると際限がなくなって,公開できなくなるので,とりあえず.
関連医学雑誌についてのimpact factorをまとめた.
ここ
なぜこんなことを調べているかというと,どこに発表するのがもっとも世の中を変えるのに効果的か(費用対効果)ということを考えているから.これが「どこに発表するのが大学で評価されるか,academic rank のpromotionに効果的か」という質問になると間違いなくimpact factorの高い雑誌という答えであることに疑いの余地はない.ところが,私が興味があるのはそうではなく,
どこに発表するのがもっとも世の中を変えるのに効果的か(費用対効果)
ということであり,多くの論文が実際には診療の現場に影響を及ぼしていない,いわゆるエビデンスー診療ギャップが存在しているため,(fidelityという言葉で下記の論文に詳しく記されている)academic journalへの発表が本当に診療の中身を変えるのに効果的かと疑問を抱かざるを得ない.実際,academic journalを読んで,自分の診療を変えた経験,頻度はどのぐらいであろうか.
Woolf et al.The Break-Even Point: When Medical Advances Are Less Important Than Improving the Fidelity With Which They Are Delivered . Annals of Family Medicine 3:545-552 (2005)
では,その代替え案としてどのような発表手段をどのような基準について選ぶかについて,readership(読者数,leadershipと間違えないよう)を基準にすることを模索する必要があると感じている.
医学雑誌読者数
これをみてみると,日経メディカルが圧倒的な発行部数であることがわかる.もちろん読者数,という点では有名タレントのブログには及ばないが.
しかしここでも,fidelityの問題がつきまとう.発行された雑誌のうちどのぐらいが実際に読まれているのか,そのうちどのぐらいの診療家が自分の診療をその結果変更するのか.何となく,個人的にはacademic journalよりも日系メディカルの方が実際に読んだものが役に立つ割合が高いようなが気がする.
ここは研究が必要なところ(すでにあるのかもしれないが)
このことは大学人やacademicianにはけしからん問題かもしれない.しかしacademic journalといわゆるthrow away journal(アメリカでは,スポンサーの広告がいっぱい入った,読み物的な医学雑誌を,軽蔑を込めてこのように呼ぶ.academic journalは本棚に保管されるが,日○メディ○ルなどは読んだら捨てられるため)の取り扱う内容には多少方針の違いがあり,どちらがよいということではない.(もちろんきちんと吟味されて書かれた,という前提がつくが)
まず,学者としての活動には大きく4種類ある.以下のページを参考にされたい.
1.The scholarship of discovery(発見)
2.The scholarship of integration(統合)
3.The scholarship of application/practice(適用、実践)
4.The scholarship of teaching(教育)
4種類のscholarship
今でも多くの大学人がそう考えていると思われるが,いわゆる学者(大学人)の仕事は1.という定義.その定義に基づけばimpact factorの高い雑誌に採用される研究をすることが学者のとしての価値である,ということになる.
私がこだわるのは,現場がどう変わるか,多くの知識の集積であるガイドラインや質の高いエビデンスのどれだけ多くを実際に患者さんに届けることができるか.現場でのfidelityの向上であり,質改善なのである.これは研究とCQI(continuous quality improvement)活動の目指すところの違いである.高血圧の治療をたとえにすると
研究:血圧を下げると健康寿命が延びる,という普遍的事実を発見,証明すること
QI:証明された普遍的事実がきっちりとできるだけ多くの患者さんに届けられるように工夫,実践の活動をすること.
実際に高血圧と病名がついた患者さんの多くは,管理目標まで血圧が下がると長生きできる,というほぼ普遍的事実があるにもかかわらずその利益の享受ができていない(管理目標まで下がっていない).このギャップには多くの障害があるとされているが(今回は省略),そのギャップを取り除く作業をQIと呼び,また別の視点からは教育とよぶ.
従来は,狭義の1の活動のみが学術活動と考えられてきたが,たくさん世の中に出る論文をわかりやすくまとめること(統合.質の高いreviewをわかりやすくまとめること),現場で体系的に質の向上に努めること(適用、実践),患者さんに,他の医療者に,研修医,医学生にわかりやすく伝えること(教育)もすべて学術的活動とかんがえられている.しかし,それぞれ,体系的であったり,計画的であったり,その効果が測定されている必要があるなど,学問として認められるには少しの縛りはある.
ただ,白い巨塔にいなくても学者として学問はできるということは間違いない.
最終的にもう一つ重要な条件がある.OHSU(オレゴン健康科学大学)の家庭医J.SaultzとS.Fields氏がいっていたことだが,「学術的活動はdissemminationをもって初めて学術的活動となる.」つまり,どれだけすばらしい活動をやっていてもそのことが世界に知らされなければ学問としての価値はないということ.「知識は人から人へ伝えられるまで何の価値も持たない」という動的知識論と整合性をなしている.つまり発表,論文.ということ.私が一番苦手なことだ.
そしてdissemminationにはwebがもっともよい.フューチャリスト宣言の梅田望夫氏の言葉を借りるまでもなく,もっとも多くの人の目にさらされる可能性を秘めているのだから.
さて,impact factorの高い雑誌での発表か,読者数の多い雑誌やメディア,またはwebでの発表か.どれが世界を効果的に変えるのだろう.新たな発見はimpact factorの高い雑誌での発表,それ以外は,うまく媒体を選んで,ということになるのだろう.
現場の臨床家は,自分たちがよいと信じてやっている様々な活動,工夫の効果測定と発表をもっと.
大学人は,純粋な知識の発見以外の学術活動(2.3.4)に対しての大学での正当な価値評価のための認識とその仕組み作りを.
P.S.現場で研究ができないわけでもしてはいけないわけでもない.現場にしか研究の種は転がっていない.しかし,圧倒的に資源が足りない.大学と現場の協働が不可欠である.
impact factorについては,下記の書籍がもっともよくまとまっている.なぜ学術集会の抄録が(suppliment:付録)なのかなども,そして,impact factorが全てではないこともわかる.
- インパクトファクターを解き明かす
- 発売元: 情報科学技術協会
- 発売日: 2004/03
- 売上ランキング: 1039447
posted with Socialtunes at 2008/02/05
1 コメント
![]() 時刻:
13:12
ラベル:
academic value,
career,
fidelity,
impact factor,
readership,
scholarship,
インパクトファクター,
研究,
読者数
時刻:
13:12
ラベル:
academic value,
career,
fidelity,
impact factor,
readership,
scholarship,
インパクトファクター,
研究,
読者数
2007/11/13
Authorship(学会や雑誌での学術発表を前提とした研究、プロジェクト)
最近著作権やauthorshipについてまじめに考えることが多い.
指導医養成などで招かれて,使った資料が,全然知らない,自分の関与しない講習会で使用されていることを何度か目にしてからのような気がする.また,うちのレジデントや,他の若い人たちと記事を書くことが多くなり,時には自分はほとんど関わっていないのに,名前を載せていることに多少罪悪感とこれでいいのだろうかという違和感が残ったり.
以下に医学的な学術活動において著作者の名誉はどのような基準を満たすと得られるのか,について,標準的なガイドラインをいくつかふまえて,私見を追加してまとめた.
自分はほとんど何もやっていないのに,準教授や,教授など医局員と思われる人の名前がずらずらと並んでいる論文を(ホントはそんなにマンパワーなしでもできると思われる程度の論文)時々目にすることもあり,scholarとしての倫理,プロ意識といったあたりを考えるきっかけになればと.(あとは,後日関係者間でもめないために)
最後の論文がそのあたりの現象を記載しています.
以下のICMJEとJAMAの基準に出きる限り合致させ、その上に、スムーズに進むように個人的な考えを追加して有ります。
1)プロジェクトの早い時期にlead author (principle author)を決めること。lead authorは出きる限り、authorの中で最大の貢献をするよう努力すること。また、projectの進行についてのマネジメントはlead authorの責任とする。
2)すべてのauthorはlead authorからauthorとしての招待invitationが有ることを必要条件とする。しかしこれは十分条件とはしない。(十分条件としては次項参照)
3)authorとしての十分条件を満たすには、以下の3つのすべてを満たす必要がある(ただしa)は純粋な原著論文には適応は難しいので主観的判断になると思われる)
a)発案、計画、データ収集、分析、データの解釈の過程において十分substantialな貢献をしていること
b)論文(学会の場合は原稿とスライド、またはポスター)の作成もしくは推敲に関わったこと(重要な知的内容に関して。単なる誤字脱字、文体の訂正だけでは不十分)
c)最終原稿の形態、内容、表記、投稿先などについて納得、承認していること
3’)グループとしてauthorを名乗る場合(xxx研究グループなど)はそのメンバー全員が上記のauthorshipの条件を満たさなければならない。そうでない場合は、そのグループの中で、上記の条件を満たすものだけをauthorとして記載する。それ以外のメンバーはacknowledgment(謝辞)に記載することはできる。
4)可能であればauthorの中でguarantor(s)(保証人)を設定する(複数でも良い)。guarantorはその論文の開始から出版までの全体の統一性について責任を負う。基本的にはlead authorがやるのがよい。
5)authorの表記順序についてはauhtor全員でのjoint decision(共同決定)による。その順序の理由について尋ねられた時に答えられるようにしておくこと。
6)acknowledgment(謝辞) 上記のauthorshipの条件を満たさないが、その研究、プロジェクトについて貢献をした人はすべて、acknowledgment(謝辞)に列挙されなければならない。(たとえば、純粋に技術的なヘルプを提供した人、執筆の助言、単純に一般的なサポートのみを提供した上司(department chair)など)
グループによるプロジェクトで、メンバーのうちauhtorshipの条件を満たさない人については、“clinical investigators” or “participating investigators,”もしくは、その役割を“served as scientific advisors,” “critically reviewed the study proposal,” “collected data,” or “provided and cared for study patients.”などとして、記載しても良い。
7)学会発表の原稿とスライド、またはポスターについては上記ほど厳密でなくても良いとは思います。
以下参考引用-------------------
*Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication
International Committee of Medical Journal Editors
http://www.icmje.org/
*JAMA
instruction for Authors
http://jama.ama-assn.org/misc/ifora.dtl
*Council on Science Editors
http://www.councilscienceeditors.org/services/atf_references.cfm
Selected References on Authorship
*Society for Neuroscience Ad Hoc Committee on Responsibility in Publishing: Responsible Conduct Regarding Scientific Communication, Draft for circulation, version 7.7, 26 June 1998.
URL:
*Multiple Authorship
The Contribution of Senior Authors
(JAMA. 1998;280:219-221)
http://www.ama-assn.org/public/peer/7_15_98/jpv71032.htm
Joost P. H. Drenth, MD, PhD
Context.—The number of authors per article has increased markedly in recent years. Little is known about the hierarchical order of authorship and its change over time.
Objective.—To assess the change in number and profile of authors of original articles published over a 20-year period in BMJ. It was hypothesized that the number of authors increased over this 20-year period and that it was the senior scientists who benefited most.
Design.—Comparative descriptive analysis of the number and academic rank of authors who published original articles in BMJ volumes 270 (1975), 280 (1980), 290 (1985), 300 (1990), and 310 (1995).
Main Outcome Measures.—The specific academic rank, order, and number of authors for each original article. Eight categories of authorship were distinguished as follows: 1, professor; 2, department chairperson; 3, consultant; 4, senior registrar; 5, lecturer and/or registrar; 6, medical student; 7, house officer; and 8, miscellaneous.
Results.—The number of original articles published per year decreased from 262 (1975) to 125 (1995). The mean number (SD) of authors per article increased steadily from 3.21 (SD, 1.89) (1975) to 4.46 (SD, 2.04) (1995). Most authors belonged to category 3, and its proportion varied from 24.7% (1975) to 22.6% (1995), while category 1 grew from 13.2% to 20.3%. Category 5 authorship dropped from 24.3% (1975) to 15.8% (1995). With regard to first authorship, category 1 more than doubled from 8.0% (1975) to 16.8% (1995) compared with category 5 whose proportion decreased from 34.0% to 24.8%. Most last authors were from category 1, 20.4% (1975), growing to 29.0% (1995).
Conclusion.—Over the last 20 years the number of BMJ authors of original articles increased, mainly because of the rise of authorship among professors and department chairpersons.
JAMA. 1998;280:219-221
0
コメント
![]() 時刻:
15:58
ラベル:
authorship,
scholarship,
学会,
学術活動,
著作者,
論文
時刻:
15:58
ラベル:
authorship,
scholarship,
学会,
学術活動,
著作者,
論文