関西での新型インフルエンザが収束の兆しを見せています。今回の弱毒性というところを根拠に楽観論を唱えていた人たちは、「それ見ろ大したことないじゃないか」というかもしれません。でもそれは、十分に準備をしていた人たちの努力で、感染の拡大が最小限に抑えられたからこその結果なのかもしれません。
しかも、夏に向けての収束も予測されていたことで、過去のパンデミック同様第2波、第3波がより大きく、毒性が強くなることの可能性、また鳥インフルエンザの流行の可能性がなくなった訳ではありません。
Cassandra (metaphor)
From Wikipedia, the free encyclopedia
多くの人には聞き慣れない表現かも知れません。Alan AtKisson,枝廣 淳子 監訳の同タイトルの本があります(原題:Believing Cassandra .最後にリンク)
古代ギリシャ神話のあらゆる予知能力を持ちながら、誰からも信じてもらえない、という呪いをかけられたカサンドラという女性がいます。
監訳者自身のHPより
カサンドラのジレンマ—地球の危機、希望の歌—
上記リンクより
プロローグ(抜粋)--------------------
美しいカサンドラは、トロイ最後の王の末娘だった。アポロン神が彼女に思いを寄せたが、カサンドラはそれを拒んだ。彼女の愛情を勝ち取るため、アポロンは「もし、おまえが私を愛してくれるのなら、未来を予言する力を授けよう」と申し出た。
カサンドラはその交換条件を受け入れ、未来を見る力を得た。しかし、彼女はどうしてもアポロンを愛することができなかったので、アポロンは激怒した。アポロンはカサンドラに授けた力を取り返すことはできなかったが、これ以上ないほど残酷なやり方で復讐をした。彼はたった一度の口づけを懇願し、カサンドラはそれに応じた。二人の唇が触れ合ったとき、アポロンはカサンドラの口に呪いを吹き込んだ。「誰も絶対に彼女の予言を信じない」という呪いを……。
こうして、カサンドラは絶望の一生を送る運命となった。まわりの人々を脅かすような危険が迫っていることが分かっても、それを防ぐことができない。カサンドラはトロイの人々に「ギリシャ軍が攻めてきます」と警告し、「トロイの木馬の中に兵士たちが隠れています!」と必死になって伝えようとした。しかし、誰も彼女の警告に注意を傾けなかった。やがてトロイはギリシャの猛攻撃を受け、陥落した。
--------------------------
以下本文37−38ページ 岡田 による引用+翻案
あなたには現在の動向がどのような結末につながりそうかが見えている。人々に、今何がおこっているかを警告し、方向転換しなくてはならないと訴えることができる。一部は信用し、行動を起こすが、大多数はあなたの警告に反応できないか、しようとしない。
あとになって、破綻的な状況が起きれば、そういう人たちは、まるであなたの予言が引き金となって破綻がやってきたかのように、あなたを非難するだろう。(予言が的中する予言者が最も非難される。)逆に、あなたの警告と、それを受けて行動した人々の活躍により破綻が回避されたとしたら、「お前の予言は外れた、嘘つきだ、予言者失格だ」というだろう。
カサンドラにとってはどちらに転んでもうれしくない結末となる。予言を信じてもらえなければ世界は破局へ。信じてもらえれば結果的に自分が間違っていたことに。
予言を伝えるタイミングも、メッセージを伝える調子も完璧でなければならない。そして予言が「外れる」タイミングも正しくなければならない。なぜなら、一度「はずれ」だということがわかったら、世間はあらゆる手段を使ってすぐに「この人のいうことは間違い」というレッテルを貼り、あなたの信憑性は崩れてしまい、それ以降は世界に対してほとんど影響を与えられなくなってしまうからだ。
さらに、ご存知のように、警告はあまり効果的ではない.人々はあなたのいうことを信じるかもしれないが、それでも何も行動を起こさないかもしれない。そして、カサンドラにとって最もつらい最悪の結末は、予言が的中してしまうことだ。
---------(引用、翻案おわり)------------
地球環境の悪化にたいして「持続可能な社会発展とイノベーション」について書かれた本であるが、現在の新型インフルエンザに関しての世の中の反応と共通点も多い。
とある私が仕えるリーダー達(現法人でのリーダーではありません)にも「新型インフルエンザ慎重論」を訴えたのですが、その時期が早すぎたのかもしれません。「不必要に住民をパニックにするだけだから、よけいな言動はしないように」と一蹴されました。(別々の2つの組織のリーダーに別々に同じことを言われました。)
世界でカサンドラとしての役割を果たすだけの才能とその役割を買って出る勇気ある人たちを嘲笑することなく、無視することなく、彼らの予言が「結果的に」外れることを願って、それぞれが行動を起こそう。そして外れた後も彼らを「嘘つき」呼ばわりすることなく、外れたことを喜ぼう。
会議で必要なのは「正解」ではなく、合意による「意思決定」と、いったん決定したらそれを何が何でも結果的に正解となるように、全員で一丸となって取り組むこと。
「すごい会議−短期間で会社が劇的に変わる!」より岡田が翻案
人は誰でも自分の視野の限界が世界の限界なのだと思い込んでいる
アーサー・ショーペンハウアー
(カサンドラのジレンマ p14より)




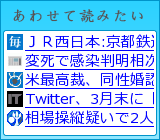



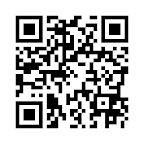




![Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2008年 03月号 [雑誌] Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2008年 03月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51LMsPvoJ2L._SL75_.jpg)