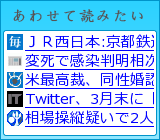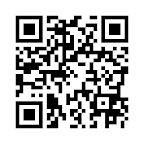多くの人の学会発表のサポートをする中でいつもお話しすることの多くは既に過去のエントリーに含まれているのでそちらを参照してもらうことが多いですが、今回、それらをまとめましたので再掲としておきます。よい研究をするためのアイデア、研究方法などは別の機会に。
抄録、タイトルの作成に関して
抄録の書き方,情報の価値 2008/02/27
http://tadao-okada.blogspot.com/2008/02/blog-post_27.html
効果的な学会抄録の書き方 2007/09/15
http://tadao-okada.blogspot.com/2007/09/blog-post_15.html
人の集まるタイトルを付ける方法(セミナーなど)2008/02/28
http://tadao-okada.blogspot.com/2008/02/blog-post_28.html
よい発表の基準の例
学会賞受賞演題スライド,読み原稿,審査基準 2008/06/16
http://tadao-okada.blogspot.com/2008/06/blog-post_16.html
誰を発表者に加えるべきか
Authorship(学会や雑誌での学術発表を前提とした研究、プロジェクト)2007/11/13
http://tadao-okada.blogspot.com/2007/11/authorship.html
そもそもなぜ発表をするのか
インパクトファクターと読者数(academic value vs fidelity) 2008/02/05
http://tadao-okada.blogspot.com/2008/02/academic-value-vs-fidelity.html
キーワード:学会 発表 抄録 タイトル authorship
2009/07/07
学会発表に役立つ過去エントリーまとめ
2008/02/28
人の集まるタイトルを付ける方法(セミナーなど)
抄録絡みでついでに、タイトルのつけかたについてすこし。
下記の本の著者が、明るい選挙推進協会 発行の 私たちの広場という雑誌の 297号 2007/11月号に「行列の出来る講座の作り方」というタイトルで連載中で、その第4回 「タイトルと講師選びは慎重に!」から抜粋。
ちなみに著者の牟田静香さんというかたは、「区の男女平等センター「エセナおおた」の活動を通し、不振だった同センターの主催講座に定員オーバー続出のヒット講座を連発するようになる」(プロフィールより)
では本題。
- 人が集まる !行列ができる !講座、イベントの作り方 (講談社+α新書 344-1C)
- 発売元: 講談社
- 価格: ¥ 840
- 発売日: 2007/04/20
- 売上ランキング: 4824
- おすすめ度

posted with Socialtunes at 2008/02/28
ここから抜粋(一部省略)
こんなタイトルでは人が集まらない!として6つのカテゴリー
*講座の目的をそのままタイトルにするストレート型
「男女共同参画セミナー」「男性の家庭参画セミナー」
興味の有る人が少ないテーマの場合は集まらない
*社会背景タイトル型
「晩婚化と男女のゆくえ」「男女共生時代と生きるわたし」
特に個を大切にする若い世代には興味が湧かない。時間、お金を割く価値が図りづらい
*疑問系
「DVって何?」「人権って何?」「今、子どもに必要なことは?」
著者の主催するセミナーで疑問系タイトルで行列ができたことは一度もないそうです。特に言葉の意味を参加者に聞くタイプのものは駄目だと。
*レッツ系
「メディア社会を生き抜こう」「地域で子育てを楽しもう」
やはり集まらないそうです。講座に参加して欲しいターゲットが明確でないから「〜しよう」になるのだそうです。
*認知率の低いカタカナ語
「アサーティブ(自己表現)トレーニング」
*相手の立場を否定したタイトル
「お父さん、もっと家庭のことに目を向けてみませんか?」「おやじ改革講座」
いくと肩身が狭くなるような気がする
ーーーー抜粋ここまでーーーー
学会の論文や発表のタイトルに当てはまらないことも一部あるが大体はこの線で応用が利く。
悪い例を考えてみよう
「麻疹について」(ストレート型)
「増え続ける糖尿病」(社会背景)
「自閉症スペクトラムとは?」「なぜ、今日本に家庭医が必要か」(疑問系)
「癌世代を生き抜こう」「次世代に必要なgeneralistを育てよう」(レッツ系)
「Crow-Fukase症候群の診断と治療」(認知率の低い)
「開業した臓器専門医は再教育が必要です」(相手の立場を否定)
学会の発表や論文を見ていると多いのが「〜について」「〜の取り組み」「〜の事例」「XXX(薬の名前)の効果」など
実際に上記の6つに当てはまらないタイトルを考えるとなると結構難しい。
STFMがすべてではないがSTFMの年次総会のたいとるみているとかなり工夫されているものが多い。是非参照にして欲しい。
実際の例を。自分の履歴書をざっと眺めて上記に当てはまらないものを探すと意外と少ない(おそらく最近意識し始めたから)
Lecture-Discussion: A Family Chart in the Electronic Age. Challenges and Opportunities for Family Oriented Medical Home. (今春のSTFMで採択、奈義ファミリークリニックの松下先生と発表予定)
Does This Patient Have Parkinson Disease? (JAMAに掲載)
Lecture-Discussion: ‘Can We Kill Many Birds With One Stone? (One CQI Projects Covers Multiple Educational Objectives) (2007年のSTFMで採択、発表)
学会発表が「楽しく!!」なるプレゼンテーションのコツ (佐藤健一、斎藤裕之先生と)
ワークショップ:「W-17 家庭医療研修医を上手に評価するために」(草場鉄周、山田康介、雨森正記先生と)
ポスター:「P-05 産科医との協力体制強化による家庭医妊婦健診継続率の増加」(西岡洋右先生と)
Family Doctors in Japan with Specialists’ Support can Provide Maternity Care for the Most of Pregnancy’ (2007 Europe WONCA)
昔は「〜について」「〜とは?」のオンパレードでした
研究や調査についてはその結果をタイトルにするのが一番です上記の最後の2件がそうです。
「xxxにおいて&&&を使うと中等度の効果がある/半減する/ZZZと同程度の効果がある/向上する」など。そのテーマに興味の有る人で、タイトルの主張がこれまでの周知の事実でない場合はまず関心を持ってくれます。
そういう意味でタイトルは抄録よりも大事です。タイトルによっては抄録すら読んでもらえないわけですから。
実は同じようなことは次の本にも書いてある。
- すごい会議-短期間で会社が劇的に変わる!
- 発売元: 大和書房
- 価格: ¥ 1,470
- 発売日: 2005/05/18
- 売上ランキング: 2359
- おすすめ度

posted with Socialtunes at 2008/02/28
会議のタイトルで
「〜について」などはやめましょう。「どうすれば〜はよくなるか」という形にしましょうと。
タイトルにも気を配りましょう。
2008/02/27
抄録の書き方,情報の価値
日本家庭医療学会,日本プライマリ・ケア学会の学術集会抄録の締切が29日に迫っている.
うちのレジデントやHANDS-FDFの修了生達とコラボで(主にお手伝いだが)発表をする予定であるが,締切に向けて,抄録の確認をする作業が中心である.
抄録を書く際に色々と自分で気をつけていることがある(それらを中心にアドバイスをするのであるが)
形式がワークショップ,口演,ポスター(学会によっては研修プログラム紹介も)によって多少違うとは思うが,共通する部分だけ書き出してみよう
意識しなければならないこと
誰に対して抄録を書いているか
1.学会の運営に関与する人:要は応募がいっぱいだったときに採否の判断をする必要が出てくる
2.当日の学会の参加者:それを呼んで興味を持ってもらう必要がある
3.その他:偶然も含めて抄録を手にする人
この三者が抄録を読むときにどのような判断を行っているかというと
1.採否を決める人,委員会
学術集会はその学会のshowcase(展示会)であり,その学会の質や性質,雰囲気を表すものである.採否に当たり,まずは気にすること
内容の質がよいか
学会の代表として出して恥ずかしくないか
学会員のニーズに合うか(質がいくら高くても,学会の使命や,対象領域と外れていてはだせない)
など
2.当日の学会の参加者
自分のニーズと合っているか
しかも新たな学びや出会いがありそうか(知っていることしかなければ時間の無駄)
要は時間対効果があるか(同じ時間帯で重なっている他の発表や,ワークショップに対して)
3.当日の学会の参加者で,最終的にその発表は聞かない人(他のものを優先した人),当日は参加しないが抄録を読む可能性のある人
自分にとって興味があり,重要な内容か
発表者とコンタクトをとって詳しい内容を聞いたり,資料をもらえないかお願いする価値はあるか
そのときにどのように連絡を取ればよいか(ネットに所属の住所や電話番号,メールなどがある,もしくは電話番号案内で調べられるのであれば名前と所属だけでよいだろう.)
自分でそのことについて調べるときに参考となるキーワード
といった感じだろうか.
難しいのは,学会の運営者(採否の審査をする人)にはしっかり内容や質の高さをわかってもらわなけばならない(そもそも採択されなければ始まらない)ので,できるだけその判断ができるように詳しく書かなければならないが,抄録だけで全てがわかってしまうと,当日の参加者にしてみればそれで全てがわかってしまったり,ネットであとから調べればすみそうだ,ということになれば,わざわざ行く必要がない,ということになり他の発表が優先されてしまう.(実際個人的には,どの発表に行かないか,ということばかり考えているので,抄録だけで全部がわかる,概略がつかめるものには足を運ぶことはありません.知り合いが発表してそのサポートのために行くのは別.)当日来てくれた人には,より詳しい情報が手にはいるとか,抄録で「おそらくこのようなないようかな」とおぼろげに期待していた以上の収穫があるとかがないと「来てよかった」ということにならないので,どれだけ抄録に書くか,というのは意外と難しい.
STFMでは応募の際に,抄録に付け加えて,結構な枚数の詳細を提出しなければならない.抄録の字数は制限があるが,それだけではやはりどの発表を採択するか決めるには情報が不十分,ということなのだろう.このようにできていると,当然抄録と詳細の読者がちがうので,非常にやりやすい.抄録は上記2.3.の人たちを対象に,できるだけ当日きてもらえるような工夫を.詳細は(研究の場合はほぼ論文になる程度のものを,ワークショップの場合は進行計画書から,主旨,目的などまで)採択してもらえるように本気で全部書くことができる(これは一般に公開されない.ただ応募の段階でかなり詰めているので,抄録だけ出しておいて,当日が近づいてデータの分析をするとかいったあわては生じない.そもそも結果の出ていないものは学会に出すべきではないのだが.)
そこで,そもそもなぜ学会で発表するのかというところにやはり立ち返らなければならないのだが,理由はいろいろあるだろう.
1.発表者であれば大義名分を持って仕事が休める.
2.発表者であれば学会の参加費用をある程度払ってもらえる
3.多くの人に是非知ってもらいたいと思っていること(研修プログラムについて,研究でわかったことについて,日常の診療で工夫していることについて,など)を伝えたい.
4.自分が熱意を持って取り組んでいること,悩んでいることと同じようなことに興味を持っている人とネットワークを作りたい.
5.枯れ木も山のにぎわい.履歴書のエントリーとして必要(特に大学にいる人たち.つまりscholarshipの証明として)
このぐらいだと思うが,そのどれかによって違ってくるだろう.1.2.5.であれば採択されることが最終目的なので,全てを書いてしまってよいと思うが,3.4.のように当日たくさんの人に来てほしい,ということであれば,やはり抄録で全てわかってしまわない(かつ,その発表を気かなければ,と思わせる必要があるが)ことも大事であろう.
まあ,抄録の字数は通常制限があるので,意図的に削らなくても,だいたい全ては入らないので,取り扱っているトピックが十分重要度や話題性の高いものであれば,必然的に,「もっと詳しく聞く必要がある」と思わざるを得ないと思われるが.
再度まとめると
自分のニーズにあうかどうか判断できるだけの具体性(来てみて全然思っていたものとちがうと満足度が下がる)
かつ抄録だけでは今一つ理解できないので/もしくは面白そうなので是非参加してみたいと思わせる表現
当日参加者の期待を越えられるだけの内容とサプライズを抄録から外しておく
当日他の興味有るセッションとぶつかって、参加を断念した人にも伝えたいメッセージ
当日他の興味有るセッションとぶつかって、参加を断念した人、参加した人が資料を希望したり、質問がある時に後からその内容にたどりつける手がかり(所属や名前、連絡先、キーワードなど)
といったあたりに落ち着くだろう.
まあ,どうひねったところでテーマが全て,というところはあるのだけれど.
診療所や一つのプログラムで少人数を対象にやった取り組みなどどうせEBM的には価値がないので発表しても無駄だ,という考えに対して
scholarship of discoveryという意味では確かにレベルが低いだろう,しかし学術活動はそれだけではない.
(4つのscholarship参照.)
「自分が興味を持っていることについての情報を効率よく集めるにはまず発信することだ」
そのテーマに興味やこだわりがある人が反論をくれたり,「こんな取り組みをしています」「xxxxという人は知っていますか?同じようなことをしているので連絡をしてみたら」「私も興味あるので今度一緒にやりませんか」などの自分で一生懸命探していても見つからなかった情報やチャンスが飛び込んでくる.同じ興味を持つ人とのネットワーキングを効率よくするには発表するに限ります.
どのタイプの学術活動(scholarship)であっても,それはdissemination(普及)もって初めて価値を持つ,というのはとあるacademicianの言葉.全くそう思う.どれだけいいことをやっていても知っていても,それがどれだけの効果を持つかというインパクトが重要.以前にそのことは少し書いた
そのことは現在の情報の価値が静的情報ではなく動的情報に移行していることとも呼応する.
つまり情報は人と人の間を行き来してその関係性とcontextの中で初めて価値を持つ.ということ.「これすごくいいアイデアだから,もっといい形にして論文にしよう」と隠し持ってなかなか取り組めず,気がついたら,他の人が同じような内容で発表していたり,すでに時代遅れになってしまったりしたことはないですか?(私はいっぱいあります)
だから,ちょっとした種であっても,とりあえず一度人に投げてみる.そこで揉んでもらう.ネットに上げて世界中に揉んでもらう.それがalways beta versionというweb2.0的なこと.
ただそれができる前提としてく動的情報の後半に書いてある「バルネラビリティ」と「自発性」.これについては最近ずっと考えているボランティア精神と密接に結びついているのであるが,またの機会に.
数日ですが抄録がんばりましょうね,皆さん.発表することが大事です.
ちなみに静的情報はこちら
まだまだこれにこだわっている古い人たちがいます.残念ですが.