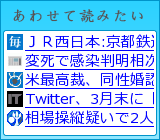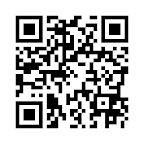Top 10 Articles January 2007 - December 2007
後半6-10番まで
6.
Section: Therapeutics
David Tirschwell
Aspirin plus dipyridamole was more effective than aspirin alone for preventing vascular events after minor cerebral ischaemia
Dec 01, 2006 11: 169-169
小規模の脳梗塞の後アスピリンにジピリダモールを追加した方が再発予防効果が高いという論文
対象は
a minor ischaemic stroke (<=3 on the modified Rankin scale) (66% of patients)
transient ischaemic attack (TIA) (28%)
transient monocular blindness (5%) of presumed arterial origin
in the previous 6 months.
Exclusion criteria included a possible cardiac source of embolism, high grade carotid stenosis, blood coagulation disorder, and limited life expectancy.
Composite end point 13% 16% 19% (2 to 32) 35 (20 to 347)
全ての血管イベント脳卒中,心筋梗塞は重症の出血による死亡が平均3.5年のフォローで
アスピリン+ジピリダモール群で13% アスピリンのみの群で16% NNT 35(ただし,95%CIが20-347)
ジピリダモールは1日400mg分2(9.5円x8= 80円弱)
またアスピリン+ジピリダモール群は34%が治療を継続できなかった(アスピリン群の治療中止は13%)脱落の多かった理由はオリジナルを読む必要あり
対象が軽症脳梗塞・TIAということ,効果の程度が不正確(NNTのCIが広い)などはあるが,それでもbenefitはあるのと,それほど高価な薬ではないので十分検討の余地はあると思います.
7.
Section: Therapeutics
C. Raina Elley, Bruce Arroll
Review: aerobic exercise reduces systolic and diastolic blood pressure in adults
Nov 01, 2002 7: 170-170
有酸素運動の血圧降下に対する効果についてのmeta分析(50以上のRCT)
最低2週間以上の有酸素運動
正常血圧の人も含めて
収縮期 -3.84 (-4.97 to -2.72)mmHg
拡張期 -2.58 (-3.35 to -1.81)
の減少(高血圧の人はもう少しだけ減少度が大きいがそれでも収縮期で5ぐらい)
アウトカムの測定がPOEMではなくDOEであること(長期的な死亡などの減少は分からない)
以上.
8.
Section: Resource review
John E Cornell, Valerie A Lawrence
Lang TA, Secic M. How to report statistics in medicine. Philadelphia: American College of Physicians, 2006. This book can be obtained from www.amazon.co.uk for {pound}33.20.
Jun 01, 2007 12: 90-91
表題の本のレビュー
9.
Section: Economics
Aslam Anis
Review: the cost-effectiveness of interventions for HIV/AIDS in Africa varies greatly
Jan 01, 2003 8: 32-32
アフリカにおける60の費用対効果に関する報告のレビュー
そのまま原文の一部を載せる(太字は岡田)
Cost-effectiveness varied greatly between interventions. A case of HIV/AIDS can be prevented for $11, and a DALY gained for $1, by selective blood safety measures, and by targeted condom distribution with treatment of sexually transmitted diseases. Single-dose nevirapine and short-course zidovudine for prevention of mother-to-child transmission, voluntary counselling and testing, and tuberculosis treatment, cost under $75 per DALY gained. Other interventions, such as formula feeding for infants, home care programmes, and antiretroviral therapy for adults, cost several thousand dollars per infection prevented, or several hundreds of dollars per DALY gained
11ドルで1例のHIV/AIDSが予防でき,1ドルで障害で標準化された1年(DALY)が得られる(単純には1年寿命が延びるとして良い)(1ドル/1DALY)(
DALYとはppt).先進国の標準的な介入よりずっと格安.(GUSTO trialに基づくtPAの費用対効果は13943ドル/1DALY,統合失調症の治療薬のDALYは
ここ)
ここにも経済法則は生きている(
限界効用逓減の法則)
10.
Section: EBM notebook
Mark D Schwartz, Deborah Dowell, Jaclyn Aperi, Adina L Kalet
Improving journal club presentations, or, I can present that paper in under 10 minutes
Jun 01, 2007 12: 66-68
表題どおり.論説