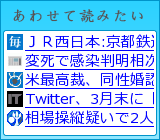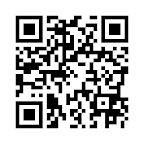下記の本にて2ページだけ執筆させていただきました。
治 療 <月刊> 3月臨時増刊号 Vol.91 ……………… 南山堂
編集:日本プライマリ・ケア学会
定価1,575円(本体1,500円 税5%)
熟練医から“日常診療のさまざまなコツ”を伝授
目次
担当分は
”院内の設備環境/ITによる情報収集と管理”のコツ
のセクションで
「莫大な情報の海でいかに有用な情報にたどり着くか」についてです。
巻頭にもありますが、依頼があったのが昨年の12月25日、本日著者提供分が届きましたので本当にスピード執筆です。
その成功の裏には
*一著者2ページだけ。複数章書いている著者もいるが実に120−130人の著者による合作。ほんの少しx莫大な人数=何らかの量/価値というウェブ進化論の主張をそのまま地で行く。厳密には少しずれるが、クラウドソーシングのような感じ。
*いっさい郵送はなし。ほとんどメール+一部fax
*包括的、網羅的であることを目指していないので、「締め切りに間に合わなければ掲載されない。それだけのことですよ」と最初から締め切りありき。(おかげで私も守れました)
といったことがあると思います。これからの執筆の一つのあり方になるのではないでしょうか。
当然執筆料、印税といったものは2ページ分。ですが。やはり自らの「経験知」を「形式値」にするナレッジマネジメントのプロセスは重要ですのでその後押しをしてくれた企画にむしろ感謝です。(これまでずっと書こうと思ってかけなかったテーマでした)
正直な所玉石混淆ではありますが、それそのものがプライマリケアが持つ「幕の内弁当」的であり、我々の仕事そのものの雑多な感じを表彰しているように思います。
逆に130近くもトピックがありますから、必ずすべての人に何らかの新しい「コツ」発見があると思います。(最近流行の言葉では「ハックス」でしょうか)