大募集中です。
公式HPはこちら
家庭医のためのマタニティーケア/ウィメンズヘルス(MCWH) フェローシッププログラム 亀田ファミリークリニック館山
2009/10/06
2009/04/06
一人でできる学び(最後はやっぱり個人)
家庭医になるべくして渡米したのはもう二昔も前のことになってしまったが,当時は「日本では家庭医になれる環境がないから」という単純な理由でした.(今考えれば,当時でも日本で家庭医になれる環境はあったのですが,情報が不十分で自分にはたどり着けませんでした.)
そのような日本の状況と,米国のレジデンシーの状況(既にProgram Requirementやら,評価やら,カリキュラムやら,しっかりと整備されていました)を比べて,当時の私は「渡米してレジデンシーに入りさえすれば家庭医になれる」という大きな勘違いをしていました.
なぜそれが勘違いだと気づいたか.
1.レジデントの最終学年半ばになって,クラスメイトと経験したコルポスコピーの数の話になったときに,あまりの差に愕然とした.「何でそんなに出来たの?」と聞くといろいろと腑に落ちる理由を説明してくれましたが,(詳細は省略)1つは本人がどのように研修をとらえていたかに大きな差があった.(乗っかっていれば何とかなる vs 自分の研修は自分で確保する)
2.そのまま,同じプログラムに指導医のタマゴとして残ったわけですが,後輩達の成長を見る中で,3年間の修了時期になっても,個人的には「家庭医とは言えないよな~というような人が時々見られる」勿論,様々な理由で研修を終了できずにドロップアウトするひともいる.
3.日本人としてアメリカで臨床研修をした人たち(家庭医療に限らず)の中に,どう考えてもお友達になれないな~というタイプの人種がいる.
4.日本でしか研修をしたことのない人たちの中に多くの「ああこの人はすばららしい家庭医だな~」と思える人たちが沢山いる
確かに指導医や研修環境が整っていることで70-80%しか良い医師になれないところを90%ぐらいには出来るかもしれませんが,逆に言うと整っていないところでも70-80%はちゃんと育つのです.ですからその環境の差が意味を持つのは環境の無いところではうまく伸びることが出来ないが,環境が整備されると伸びることの出来る10-20%(この数値は任意なので,勿論この差が80%ぐらいある場合もあるでしょうが)の人たちに過ぎません.
同様に,左記の例にあるように,同じ環境でも当然結果の差は出るわけでその差は個人に帰結する訳です.
ということで,良い環境にいても,そうでない環境にいてもより多くのことを学ぶために,学び方を学ぶ,工夫する必要があるわけです.
1人で出来る学びにも6種類ほどあるようですが,そのうちの比較的簡単に取り組める3つについてまとめています.
うちの研修医の中にも,見学に来る人たちの中にも,懸命にメモを取る人たちがいます.長期的にどのような差になるか.(メモ=>より良くなるという保証はないですが,そんな風に思えます)
今年の家庭医療学会による第21回 医学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナーでは,自分自身の努力と工夫でどこまで学びを最大化できるか,そんなサムライのようなストイックな学び方について考えるセッションを予定しています.
一人でできる学び
2009/04/04
臨床上有用なリンク集
新年度でうちへも4名の家庭医のタマゴがやって来て研修を始めました.
又研修環境の整備をいろいろとやっています.
もうずいぶん前から運用をしていますが,頻繁に話題になるリンクを集めてリンク集として公開してあります.
こんかいその多くについて,特にガイドラインを中心に,再度リンク切れの確認,新しくなっているガイドラインのupdate,いくつかのリンクの追加などmajor updateをしました.
是非皆様の施設でもご自由に使用ください.
臨床上有用なリンク集
2008/08/16
専門家というのは、自分の専門においておかしうる間違いをすべて知り尽くした人のことだ
小さな、静かなる持続の力 | lifehacking
より(途中何カ所か省略)
陶芸のクラスで、クラスを二つに分けて、作品の「質」と「量」で評価をしたところ、「量」をこなした方には「質」も付いてくるようになったというのです。このことは、理論立てて考えるよりも先にやってしまう方が早い、また失敗から多くを学べるということを示していると思えます。
また、これが陶芸のというのも注目に値します。陶芸などの芸術は「無駄の排除」あるいは「デザインの欠如」がかえって完成度を増すことが多いですので、数をこなすことはクリエイターたちの手つきから陶芸にとってむだな部分を削ぎ落としていった結果とも言えるものです。
まずは始める。質はあとからついてくる
才能云々よりも、まずは作り出すこと・作っている状態を持続することが、十中八、九、いや、百中九十九くらいの場合は正しい選択になるのだなあ、ということを、いろんなことを小難しく考える癖のある自分は、毎日のように痛感しています。
物理学者ニールス・ボーアは「専門家というのは、自分の専門においておかしうる間違いをすべて知り尽くした人のことだ」と言っています。おかしうるすべての間違いというのは、膨大な量です。大学のとき、理論物理学は論理的に正しいことだけを鋭く細く探求する学問だと思っていたときに、この言葉に接して愕然としたのを覚えています。
こうしてみると、ただ量を生み出すだけでなく:
量をたたき出して、その分野における知識を地と肉に覚え込ませるフェーズ
一定量を持続的に作り出すことによって、生産性の高い状態を自己フィードバックで維持するフェーズ
この二つがからみあっているように見えます。「自分の能力が低い」と思っている人は、「一度まとめて勉強しよう」などと考えずに、毎日最小限の行動を持続して、ゆっくりとそれを広げてゆく方が効果があるのではないでしょうか。
質より量に学ぶ | Radium Software
引用ばかりだが,言い尽くされている感があるので,追加することはありません.
たくさんやろうとすればするほど,たくさんやればやるほど,
「時間的効率」に意識的・無意識的に直面せざるを得ないため,無駄がそぎ落とされる.
しかしながら,
私の持論
「practice makes perfect(繰り返しによって完璧になる)」は間違いである.繰り返しによって確実になるのは,「あなたが繰り返しやっていること」であり,間違ってやりかたを何度も繰り返しやればそれが確実になり,余計に変更が困難になる.
からすると,数やるだけではダメで,やはり,1回1回毎にうまくいったこと,行かなかったことを検証し,次のトライに活かす,いわゆるreflective practiceでなければ改善は望めない.とおもいます.
practice makes perfect(繰り返しによって完璧になる)
改め
reflective practice makes perfect(思索を伴う繰り返しによって完璧になる)
結局Kolbの学習サイクル を何回回すか.ということ.
そして
「専門家というのは、自分の専門においておかしうる間違いをすべて知り尽くした人のことだ」
は名言.
2008/04/02
完全な指示を出すための7つの要素
自分の意見はほとんどありませんが。。
人が多くなるにつれて、熱意、やる気、根性、といった精神論だけではうまく行かないことが増えてきている。また、これまで数日かかって教えていたことをもっと短時間でとりあえずの形にする必要性が高まっている。
- 仕事の目的(より高いレベルの目標)
- 仕事の目標(望ましい結果のイメージ)
- 計画の一連の手順
- 計画の論理的根拠
- 行うべき重要な決定
- 反目標(望ましくない結果)
- 制約及びその他の注意点
完全な指示を出すための7つの要素 - *ListFreak
最も丁寧なリスト、という事で、すべての指示にこの項目すべての必要はないでしょうが、一度検証してみるのに良いリストといえるでしょう。
反目標(望ましくない結果)というのが重要だそうです(道を説明するのに、XXが見えたら行き過ぎとか、OOをしないように気をつけながらとか)
以下の本にこういったリストがまとめられています。
- リストのチカラ [仕事と人生のレベルを劇的に上げる技術]
- 発売元: ゴマブックス
- 価格: ¥ 1,575
- 発売日: 2008/02/27
- 売上ランキング: 608
- おすすめ度

posted with Socialtunes at 2008/04/02
オリエンテーション
新人の時期です。
オリエンテーションは必要なのか。必要だとしたらどのぐらいの期間? なにをやる?
今からでは今年のものの変更には間に合わないかもしれませんが、参考までに他施設での取り組みを
週刊医学界新聞 第2735号 2007年6月11日
2週間で研修医を鍛えあげる方法 市立堺病院(大阪府堺市)
市立堺病院のオリエンテーションは「グループ制でのShadowing」の導入や「仕事人リスト」「失敗リスト」の活用によって年々ブラッシュアップされ,ほぼ完成形に近いという。課題としては,後期研修医のスタート(後期のオリエンテーションは現在1週間)を改善したいとのことだ。
「仕事人リスト」「失敗リスト」という言葉がいいですね。
この理論的裏付けはあとで。
週刊医学界新聞 第2735号 2007年6月11日
病院理念を反映した他職種や地域医療の体験 東葛病院(千葉県流山市)
――他職種体験も重視されています。このねらいは何でしょう。
下 チーム医療の中で医師にはリーダーとしての役割が求められるわけですが,そのためにはコメディカルのパフォーマンスを十分に知る必要があります。医師はいったん伝票を起こせば終わりですが,その伝票を受けて仕事をしているコメディカルがいるから業務が成り立っているわけです。朝出した指示を2時間後に変えれば,指示を受ける側はいかにストレスを感じるか。医師からしてみれば,病状は刻一刻と変化するのだから変更も仕方ないかもしれません。でも,そういった時のちょっとした配慮が大切なのですね。
組織運営の重要なことは組織構成員が最大のパフォーマンスを発揮できるようにすること。ある部門のメンバーが簡単にできる仕事を、そのことを知らないために自分で苦労して、時間かかってやって、そのメンバーは手持ちぶさたにしている。
相手の立場に立った連携ということと同じぐらい人財を効果的に利用する、という意味では、他職種の人たちがどのような仕事ができるかを把握することは重要です。うちのオリエンテーションでも数年前から導入しています。うちは「他職種体験」まではいかず「見学」ですが。
川島篤志氏、下 正宗氏ともに良く知った間柄。共に初期研修医が対象なので、私の仕事とは少し異なりますが、他施設で同志が頑張っていることを風の便りで知ることで自分がさらに頑張って行ける気がします。
今月から、我々の施設でも家庭医を目指す4名の後期研修医と1名の初期研修医が研修を始めています。最初の1か月はオリエンテーションと称して他の11か月ではやらないさまざまな取り組みをするのですが、今年もまたいくつもの新しいアイデアを試験的に導入する予定です。
一つだけ先述の記事にからめて。レジデントからのアイデアで、入院ではありませんが、受診体験を新人にしてもらいます。受診される方の待つ時間の長さとか(意図的に待たせているわけではありませんが)、患者側の視点から我々の診療がどのように見えているか、などをまだ仲間として完全に打ち解ける前に外部者の視点で我々の診療の改善点も見つけてもらおうという意図も含まれています。どうなることやら。




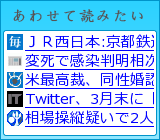



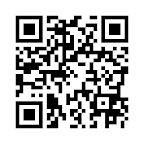


![リストのチカラ [仕事と人生のレベルを劇的に上げる技術] リストのチカラ [仕事と人生のレベルを劇的に上げる技術]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21k6wQBPz3L.jpg)